ホーム > 組織でさがす > こども家庭部 > 県民活躍推進課 > 青森県女性ロールモデル 板垣美保さん
関連分野
- くらし
- しごと
- 男女共同参画
更新日付:2014年11月7日 県民活躍推進課
青森県女性ロールモデル 板垣美保さん
まずは楽しむ努力をしてみてください。
そうすれば、身の回りに隠されているヒントに気づけるはずです。
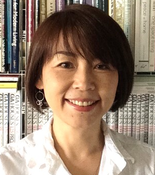
一級建築士 板垣 美保 さん(青森市)
【プロフィール】
高校卒業後、地元の一般企業に勤めるが、設計事務所に入所。平成14年に独立し、「Craftwork建築計画工房」を設立。平成15年に行われた「フォレストモア2004木の国日本の家デザインコンペティション」で、「語らいの家」が優秀賞を受賞。
板垣美保さんの主な分野 「起業」「専門職・研究職」
チャレンジのきっかけは?
記念すべき独立の第一歩
長年勤めていた設計事務所から独立するつもりはありませんでしたが、自分の中のどこかに「このまま建築の道を進んでいっていいのかな」という迷いがありました。考え抜いた末に、「一回、建築から離れよう」と決意して事務所を辞めたのですが、そんな矢先に、家を建てたいという相談が私のところに舞い込んできました。事務所を辞めたばかりだったため、依頼を受けるかどうか迷ったのですが、家を建てたいという建て主さんの切実な話を聞き、思い切って引き受けることにしました。
ですが、独立してから初めての仕事は、周囲に前例がないような特殊な家造りが必要でした。建て主さんがアレルギー体質の方だったため、家造りにもアレルギー対策が求められたんです。材料の検査も必要になるため、工期も通常より8ヵ月と長く、建築業者とも綿密な打ち合わせを行いながら、なんとか建て主さんの依頼通りのものを建てることができました。独立して最初の仕事ということもありましたが、特殊な家造りだった為、私の思い入れも相当強かったですね。そこで自分がどこまで通用するか知りたくなり試しに建て主の承諾を得てコンペティションに出してみたら、ありがたいことに賞を頂くことができました。それが少し自信となりこうして、試行錯誤した最初の家造りが記念すべき独立の第一歩になったというわけです。
これまでのみちのり
原点は、「モノ作りが好き」ということ
もともとは地元の一般企業に勤めており、建築の仕事に強い興味があったというわけではありませんでした。ですが、モノ作りが好きだったので、働きながら武蔵野美術大学通信教育学部に入り通信教育を受けるという二足の草鞋の生活をしており、そこで出会った大学の先生が、形として残すことができる建築の面白さを私に教えてくれました。
そんな折、私がいつも製図用品を購入していた文房具店の店主から設計事務所を紹介され、試行雇用からスタートしました。その後建物の設計や、現場での打ち合わせがどんどん楽しくなってしまい設計事務所の仕事一本に専念し独立するまで長年勤めさせていただきました。
驚きと感動の現場
設計事務所に勤め始めた頃は、上司が私にいろいろなことを経験させてくれました。失敗してもいいから行ってこいと、現場や役所などいろいろな所に送り出してくれたんです。
「すごい!形になってる!!」というのが、私が初めて現場に行った時の感想です。二次元の図面からできる三次元の空間を見てただひたすら感動しました。
これはこうやってできているんだ、何でできているんだろう。「難しい」と感じるよりも、まずは「すごいな」という尊敬や感動を受けながら仕事をしていました。
当時、未熟者の私は図面を描くため、建物の骨組を理解しなければならず上司や先輩からの指導後はそれを理解したくて直接現場に走る事がたびたびありました。そこでは現場監督や大工さんにしこたま怒られて帰ってくるということの繰り返しで「お前、こうやって図面を書いているけど、これじゃ建たないんだよ」と怒られ、「あ、そうなんだ」と納得するという日々でした。ですが、理解する為に現場に走る状況をみた上司が業者さんに、「こいつは修行中で全然ものを知らないから教えてやってくれ」とフォローをしてくれたおかげで、その後業者さんもいろいろと教えてくれるようになりました。
今思えば、設計事務所の上司や先輩はさることながら現場の業者さんにも相当鍛えられましたね。
独立してから
建築業界ではたいてい20代後半に独立をする人が多いですが、私が独立したのは30代後半でした。事務所を辞めた矢先、思わぬきっかけで独立することになりましたが、大変というよりはむしろ楽しかったです。全てが自分の責任になりますし、とにかく迷うよりも決断しなければならず、決断したからには『オーナーの為にいかにいいものを作り提供できるか』だけを考えました。
修行時代に、なにか問題が起こったとしても、時間をかければほとんどが解決できるものだと育てられたので、変に気負って悩むことはせず、じっくりと解決策を考えていきました。独立し数年後に子どもが生まれ、自分に子どもができると、建築の面でも子どものことを考慮し、子どもが安心して遊び学べる家とは何かということを考えるようになりましたね。また、子どもは何事においても「なぜ?どうして?」という疑問を持っているので、疑問を持っていろんな角度から捉えてみるという初心を私に思い出させてくれました。小さい子どもがいると、生活空間を提案する仕事にとても役に立っています。
建築士ならではの楽しさ
建築士といってもいろいな専門分野があり、わかりやすいところで設計では意匠設計や構造設計、設備設計があります。
私が主に手がけている仕事の分野は意匠設計に入ります。イメージしたものを図面化し、その意匠図面と照合する監理業務を現場でおこない施工業者が造り完成させます。
建物のデザインはデスクワークのみと思われがちですが、実際は現場に足を運んで業者さんと打ち合わせをすることも頻繁にあります。本音を言うと、建物ができあがる工程の中で最後には隠れてしまい表に出る事はない骨組みの部分が一番好きです。
また、私は家の中のいろいろなところに小技を散りばめる設計が好きです。そういう小技のほとんどが、建て主さんの言葉がヒントになって生まれたものです。プランの段階で建て主さんからの意見を引き出し、コミュニケーションをたくさん取ることで、私のアイディアの貯金もどんどん増えます。そういう意味では、建て主さんとの何気ない会話の中にあるヒントを探し出し、それを具現化できたときの楽しさや嬉しさは、建築士ならではだと思います。
現在の活動状況や今後の目標など
常に進化する建築に追いつきたい一心で
作るのが好きなので、基本的に仕事を辛いと思ったことはありませんが、想像の世界を具現化するという作業はかなりハードです。建て主さんに期待される分、どう表現すればいいんだろうか、という気持ちが常にあります。はっきり言って、自分との戦いです。人に左右される仕事ではないので、自分の中でどこまで良いものができあがるか、ただそれだけです。
また、建築の勉強に終わりはありません。生きていくうえでの生活全てが建築というものに関わります。気候風土もそうです。それを考えながら古きを暖め新しきを知るという勉強を怠らず、その糧のうえで良い設計ができるように努力をおしまないようにしていきたいです。
建築士はオーケストラの指揮者
建物も人と同じで、手をかけてあげないといい子に育ちません。手をかけるというのは、現場にきちんと足を運んで、その成長過程を確認するということです。
いろいろな職人さんがよかれと思って作業しているのではありますが、やはりその意向が食い違う場合があります。設計する側の意向と、造る側の意向のギャップです。建て主さんと私、つまり設計者側の合意点は工事に取りかかる前の段階で既にできあがっていますから、その合意点について業者さんと協議することで建物も、とてもいい子に育つのです。
家造りはオーケストラと一緒で、言うなれば建築士はオーケストラの指揮者です。いいものを造りたいなら、業者さんの良い部分をすべて引き出してあげなければいけません。その引き出したものを、建て主さんが望んでいる家としてまとめあげるのが、私たち建築士の仕事だと思っています。
何かを言われたらきちんと答える、しかも100倍返しで
作業をしている職人さんはだいたい男性の方が多いです。この業界はまだ女性が少ない為特にそうですが、女性は現場の事をあまりよくわからないだろうと思われがちです。私が現場に入るときよく洗礼を受けます。「これ分かる?」と、複雑な質問をされて、答えられないでいると「こんなのも分からないの」という感じで物を言われかねません。職人さんはそれぞれ自信を持ち作業しておりプライドも高いので、中途半端な対応をしてしまいますと、こちらの意図する物ができなくなってしまいます。
また、私は言われたら言い返すタイプなので、半沢直樹ではないですけど、「何かを言われたらきちんと答える、しかも100倍返しで」という姿勢でいます。そうすると、職人さんも「こいつはやばい、ちゃんとやらなきゃ。」という姿勢に変わります。ですから、新しい現場や新しい地域で仕事をする場合は、業者さんや職人さんに私の意向をはっきりと訴えかけるようにしています。
今後の活動
独立後に子どもが産まれましたが、やはり自分が事務所の代表者なので、子どもにあまりかまってあげられず、うちのスタッフにも子どもの面倒を見てもらいました。
出産をした後も女性が働き続けるためには、やはり周囲の環境が大事だと思います。子どもを預ける場所がなかなか見つからないので、女性が働く企業は子どもを見てくれる環境を社内でも整備してあげることが必要です。
また、子育てに関する悩みを持っていても相談しに行くところがない、相談に行きづらいと感じている人が、青森県内にはたくさんいると思います。そういう人たちが気楽に来ることができて、何でも話せるような何かをやりたいという気持ちが自分の中にあるので、今後は仲間を作りながらそういう活動もしていきたいと思っています。
これからチャレンジする女性へのメッセージ
オールラウンドプレイヤーよりもチームワーク
自分できちんとしたものを造りたいと思っても、ひとりの力ではどうにもならないことが必ず出てきます。建築の仕事だって、建築士の私だけでは建物はできません。建て主さんの希望があって、建築士の図面があって、そして業者さんの技術があって、初めて建物ができあがります。
なんでもできるオールラウンドプレイヤーが優秀だと言われますが、そうではありません。大事なのはチームワークです。得手不得手を補った人たちこそが一流のチームであり、そのチームがいいものを造りあげるのです。どの仕事もそうだと思いますが、やはり仕事をするには、とことん協議をして周りを味方につけていくのが一番だと思います。
まずは楽しむ努力を
長年勤めていた事務所の上司が、「日常生活や遊びを楽しまないといけない。その中に、実はたくさんのヒントが隠れていて、全部が勉強になるんだから」と言っていましたが、まさにその通りです。「こうなんだ」と決めつけてしまうと、本当にそれ以外のヒントに気づけなくなってしまいます。そうではなくて、「これはなんだろう」「なんでこうなるんだろう」と多面的に考えることで、身の回りに隠されているヒントに気付くことができ、表現へとつながっていくんです。
どの仕事にも通じることですが、「ただ働いているだけ」という感覚を持ってしまえば、その仕事の楽しさには気づきません。子育てだって同じです。まずは楽しむ努力をしてみてください。そうすれば、身の回りに隠されているヒントに気づけますし、気づいたらめいっぱい楽しんでいる自分がいるはずです。
平成26(2014)年9月取材
青森県女性ロールモデル事例紹介に戻る



